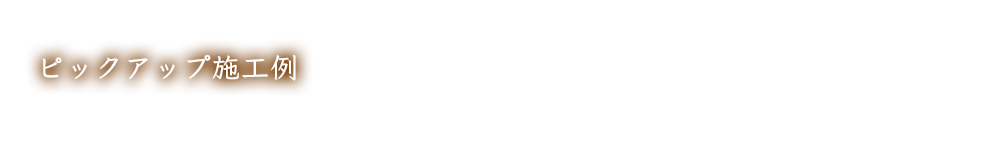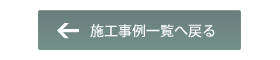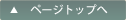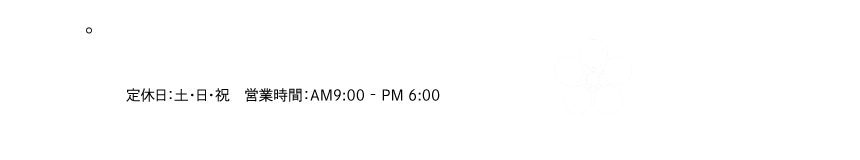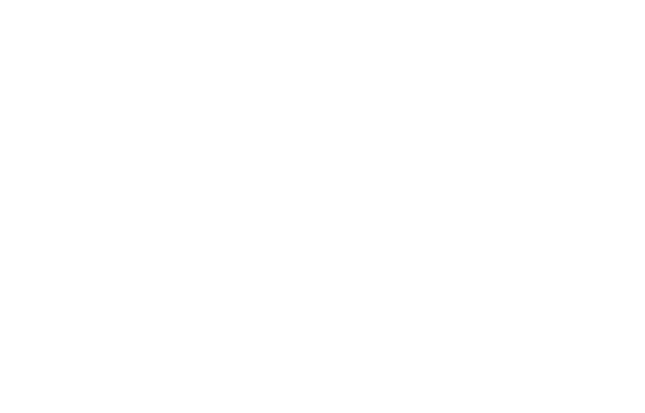- 吟優舎HOME
- ピックアップ施工事例一覧
- 施工事例
ピックアップ施工事例
山手の街並みに佇む町家リノベーション 京都市東山区
京都市東山区、山手の静かな住宅街に佇む一軒の町家。
奥様が子ども時代を過ごされた築90年以上のご実家を、ご夫妻が「終の住まい」として再生したいと、ご相談いただきました。
長い年月の中で幾度か改修され、外観はかつての面影を失っていましたが、古い梁や建具には、まだ確かな魅力が残っていました。
「この家は、きっとまた美しくなる」——そう感じ、ご夫妻の想いに寄り添いながら、町家らしさと心地よさを両立させた再構成を目指しました。
思い出の詰まった家が、ご夫妻のこれからを育んでいく場所へ。その歩みをご紹介いたします。
☆工事の過程はブログ2023年9月25日からご覧いただけます。
奥様が子ども時代を過ごされた築90年以上のご実家を、ご夫妻が「終の住まい」として再生したいと、ご相談いただきました。
長い年月の中で幾度か改修され、外観はかつての面影を失っていましたが、古い梁や建具には、まだ確かな魅力が残っていました。
「この家は、きっとまた美しくなる」——そう感じ、ご夫妻の想いに寄り添いながら、町家らしさと心地よさを両立させた再構成を目指しました。
思い出の詰まった家が、ご夫妻のこれからを育んでいく場所へ。その歩みをご紹介いたします。
☆工事の過程はブログ2023年9月25日からご覧いただけます。
※画像をクリックすると拡大表示します。
さりげない個性が光る玄関
以前はごく一般的な玄関だった空間を、墨モルタルの土間にカラフルな飾りタイルをちりばめた玄関へ。淡い色調の格天井とアンティーク風のペンダントライトがアクセントになっています。
静かな品格が漂う座敷へ
新しくなった和室には、アンティークの引き戸と、京唐紙の襖をあつらえました。建具は、滑らかに開け閉めできるようきしみやゆがみを調整。
襖の唐紙には、職人の手による繊細な文様が浮かびます。
光と風が通うダイニング
本来の町家には、両サイドに窓がありません。このお宅も庭に面した窓しかなく、また庭の向こう側にも部屋があったため、室内が暗くなっていました。
庭に面する開口を広げ、採光と通風を確保。視線が遠くへ抜け、光と風が巡り、広々と開放感のあるダイニングに姿を変えました。
光を取り戻した吹き抜け(火袋)
改装前、天井の奥にわずかに残っていた高窓の痕跡。それは、かつてこの町家に「火袋」があった名残でした。閉ざされていた天井を開き、元の構造を活かして火袋を復元。高窓から光が差し込み、心地よい吹き抜けに生まれ変わりました。
庭を眺めるくつろぎの時間
少し暗めだった脱衣所と浴室は、明るい光が差し込む空間へ。浴室の窓はできるだけ低く設置することで庭を望める設計に。
湯に浸かりながら四季の移ろいを楽しめる、癒しの時間が生まれました。
吟優舎では、庭を囲むように居間、浴室、洗面室、お手洗いを配置し、光と風を取り込むプランをご提案しています。
やわらかな風景をつくる庭
離れを解体して物干し場を設け、その傍らには紅梅の枝垂れ梅やミヤコワスレなどが植えられ、風情ある趣を添えています。吟優舎の造園は、植栽はもちろん、灯籠や蹲(つくばい)、手水鉢、石に至るまで、すべて自らの目で選び抜いた素材を使用。
設計から施工まで一貫して手がけ、熟練の造園職人とともに、お客様だけの庭をかたちにしていきます。
施主様の過去の思い出と、これからの暮らしをつなぐ町家。
閉ざされていた火袋に光が戻り、広々としたダイニングキッチンのある町家へ。そして季節を映す庭の緑が、日々の暮らしに彩りを添えます。
京都・東山という土地に根ざし、ご夫妻の新たな物語が、ここから静かに紡がれていきます。
© GINYUSYA. All rights reserved.