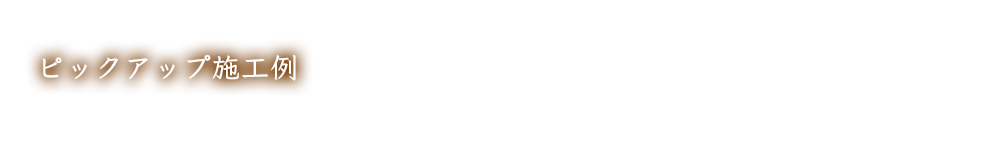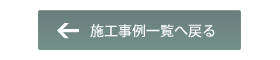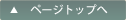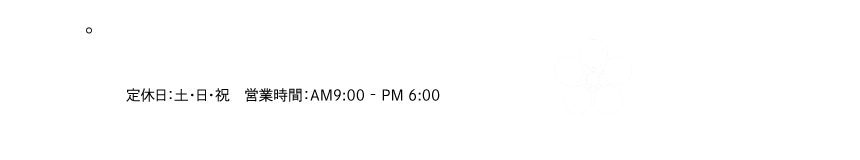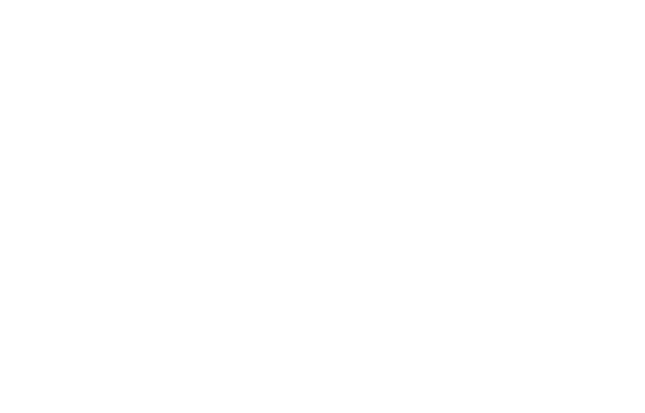- 吟優舎HOME
- ピックアップ施工事例一覧
- 施工事例
ピックアップ施工事例
大正ロマン数寄屋造りの町家リノベーション 京都市下京区六条
京都市内でも町家が多く残る下京区。
今回リノベーションを手がけたのは、築100年を超える由緒ある京町家です。
元の家主は骨董商だったとのことで、屋内には茶室(数寄屋)など、こだわりの意匠が随所に見られました。
「数寄屋(すきや)」とは、もともと茶の湯のための空間(茶室)やその付属建物を指す言葉。現在では、その意匠や技術を取り入れた高級和風住宅なども「数寄屋造り」と呼ばれています。
今回は「数寄屋造りの町家リノベーション」をテーマに、趣ある意匠を残しながら、施主様ご家族にとって暮らしやすい住まいへと生まれ変わった様子をご紹介いたします。
☆工事の過程は2024年8月15日からご覧いただけます。
今回リノベーションを手がけたのは、築100年を超える由緒ある京町家です。
元の家主は骨董商だったとのことで、屋内には茶室(数寄屋)など、こだわりの意匠が随所に見られました。
「数寄屋(すきや)」とは、もともと茶の湯のための空間(茶室)やその付属建物を指す言葉。現在では、その意匠や技術を取り入れた高級和風住宅なども「数寄屋造り」と呼ばれています。
今回は「数寄屋造りの町家リノベーション」をテーマに、趣ある意匠を残しながら、施主様ご家族にとって暮らしやすい住まいへと生まれ変わった様子をご紹介いたします。
☆工事の過程は2024年8月15日からご覧いただけます。
※画像をクリックすると拡大表示します。
装飾格子が美しい外観
上下階の構造がほぼ同じ高さで構成される「総二階形式」の京町家。1階には出格子、2階には縦格子を備え、本瓦葺きの屋根が町家らしい風情を今に伝えていました。
その趣を活かしつつ、アルミサッシだった玄関建具を新たな木製格子戸に取り替え、昔ながらの意匠を復元。
1階の出格子は特徴的な装飾をそのまま生かし、塗装と補修を施しました。
木部は焼き板風の古色を活かしたシックな仕上がり。土壁風の壁とマッチしています。
通り庭を活かしたガレージとシンボルライト
玄関まわりの「通り庭」を、施主様のご希望により駐車スペースとして活用。元の通り庭の奥行きを生かしつつ、奥に引き込むようにガレージを新設しました。
印象的なのは、天井に設置されたアンティークライト。
もともと2階に吊るされていたガラスと真鍮の照明器具を、ガレージの中央に移設しました。
繊細で重厚な佇まいが、この町家の象徴となっています。
3種の天井意匠が迎える玄関
ガレージの奥には、表玄関と勝手口をそれぞれ新設。表玄関の正面壁に見える黒い柱は、もともとの大黒柱です。この家の歴史を象徴する大切な存在だからこそ、あえて隠さずにデザインに生かしています。表玄関の天井には、異なる3つのデザインが共存しています。
繊細な編み模様の「網代天井」、伝統的な「竿縁天井」、そして歴史を感じさせる「旧来の天井」。時間の層を感じさせる、味わい深い玄関空間です。
猫足スタンプと金魚柄タイルの勝手口
勝手口の土間には、猫好きの施主様がご用意された「猫足スタンプ」を使用。職人がひとつずつバランスを見ながら丁寧に押し、あたたかみのある土間が完成しました。その先には、金魚柄のモザイクタイルが可愛らしい手洗いを設置。市販のガーデンパンとブロックに、タイルを組み合わせて一体感のある仕上がりに。施主様のこだわりが詰まった、とても可愛らしい一角になりました。
建具を再利用した収納
勝手口のそばには収納スペースを設けました。扉には、元の和室で使われていた「網代の建具」を再利用。味わいある風合いが、新しい空間にも自然と馴染んでいます。奥に設置したアンティークライトも、もともとこの家にあったもの。歴史ある素材が新たな場で輝きを放ち、町家の記憶が静かに受け継がれています。
通り庭からつながるウッドデッキ
京町家特有の細長い間取りを活かし、玄関から奥へと続く通り庭をウッドデッキにリノベーション。屋根材は元の透明な波板を活かし、全天候型の物干しを設置しました。天気に左右されることなく洗濯物が干せる、暮らしに寄り添う空間へと生まれ変わりました。
キッチンカウンターのあるダイニングキッチン
かつて台所は通り庭の奥にあり、母屋から靴を履いて移動する必要がありました。そこで新たなキッチンは、家の中心である玄関のすぐ横に再構成。ご家族が自然と集まる、明るく開放的なダイニングキッチンが誕生しました。キッチン前には造作のカウンターを設置。「ただのカウンターではないものを」という施主様のご希望に応え、なぐり加工を施した土台にモザイクタイルをあしらい、機能性と意匠性を兼ね備えた印象的な空間に仕上げています。
奥庭を臨むリビング
吟優舎が設計で最も重要とする部分が「庭まわり」。奥庭に面するリビングの窓は、可能な限り開口を広くとり、端から端までガラスで構成。自然光がふんだんに差し込み、季節の移ろいが美しく映えるリビングになりました。
ブラインドは、半開調整が可能なタイプを採用。日差しを柔らかくコントロールしつつ、緑あふれる庭の風景をいつでも楽しめるように工夫されています。
町家の中心となる庭
奥庭は、リビング・渡り廊下・寝室の三方に囲まれた、いわばこの町家の中心。通風と採光の要であると同時に、暮らしの潤いをもたらす大切な空間です。植栽や石の配置には施主様と吟優舎のこだわりが詰まっており、四季折々の表情を感じられる美しい庭に。かつての静けさを引き継ぎつつ、新しい暮らしを引き立てる中庭として再生されました。
奥へと続く渡り廊下
もともと奥には離れのキッチンがあり、ご家族はそこへ靴を履いて移動されていました。リノベーションでは、奥の部屋と続く生活動線を新たに確保。庭に沿って渡り廊下を設け、快適な室内移動が可能になりました。半屋外であることの多い京町家の廊下ですが、新たな廊下にはガラス窓を設置し、断熱性と開放感を両立。冬は寒さから守り、春夏秋は庭の緑と光が心を和ませてくれます。
やさしさに包まれる高齢のお母様のお部屋
渡り廊下の先には、高齢のお母様の部屋が位置しています。庭に面した大きな窓は、やわらかな光が差し込みます。庭の緑を眺めながら、静かにくつろげる場所を設えました。またベッドのそば、壁の低いところに、3つのブザーを設置。万が一何かあった場合の小さな備えに、安心が宿ります。施主様の、お母さまへの深いご配慮が生んだお部屋です。
風情を継ぐ2階のリビング
2階中央には、ご家族で過ごすリビングスペースを設けました。リビングから寝室への入口は、茶室の入口をイメージしたアーチ開口を採用。茶室においてアーチ開口は「火灯口(かとうぐち)」と呼ばれ、給仕口や茶道口として用いられます。その狭い入口を通ることで茶室という特別な空間へと誘われるように、弊社のアーチも別空間への気分を高める装置の役割を担っています。
このリビングの特徴のひとつが「天井」です。元々この家にあった趣深い意匠を残しつつ、新たな空間と調和するよう整えました。古き良き美を受け継ぎながら、新たな日常に寄り添う場所です。
水屋跡を活かした2階トイレ
2階リビングの隣に設けたトイレは、もともとは茶席の水屋(茶席のための道具を置き、水を扱う場所)があった場所。天井はそのままに残し、静けさと上品さを引き継いでいます。壁と扉には、施主様の思い出のステンドグラスを組み込みました。暮らしの中に個人の記憶が息づく、特別な空間となっています。
防音性に配慮した寝室①
2階には、ご家族それぞれの寝室を配置。その一室には、施主様の「いびきを気にせず眠りたい」というお声に応え、防音効果のある遮音シートを壁内部に設置。床はアカシア材のフローリング、天井は煤竹(すすたけ)を配した船底天井、壁紙はやわらかなトーンで、落ち着いた上質な寝室に仕上げています。
寝室②ベッドサイドテーブルの造作
あらかじめご購入予定だったベッドサイズに合わせて、サイドテーブルを造作。就寝中でも手が届く位置に照明のスイッチを配置し、細やかな使い勝手にも配慮しました。家具の配置やサイズをあらかじめ想定した設計プランニングは、吟優舎の得意とするアプローチ。コンセントや照明もぴたりと合い、住まわれてからの満足度がぐっと高まります。
寝室③デスクスペースへと再構成
もう一室の寝室では、あらかじめ設置予定だったデスクに合わせて、床の間の一部をワークスペースへとリノベーション。ご購入いただいたテーブルのサイズをもとに、ぴたりと納まるようプランに反映しました。既存の布襖はあえて残し、プリンター置き場として再利用。かつての意匠と新たな暮らしが自然に調和する一角です。
趣向を凝らした数寄屋造りの京町家が、現代の暮らしに寄り添う住まいへ。
風格ある町家の意匠を尊重しながら、時を重ねた建具や照明、天井の趣を丁寧に生かし、ご家族のこれからの暮らしにふさわしい機能と美しさを備えた空間へと生まれ変わりました。光と風が巡る庭、家族をつなぐ渡り廊下、思い出が息づく素材の数々――
新たな命を吹き込まれたこの町家から、新しい物語が静かに紡がれていきます。
© GINYUSYA. All rights reserved.